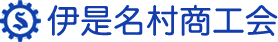事業者の皆さまへ
マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応
まずはじめに
| マイナンバー制度は、 ①行政を効率化し、 ②国民の利便性を高め、 ③公平・公正な社会を実現する社会基盤となり、 平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。 ・マイナンバー(個人番号)は平成27年10月から国民の皆さまのもとに届きます。10月以降に住民票の住所地に、マイナンバーの「通知カード」が送られます。(通知カードは紙製のものです。) ・平成28年1月以降に市町村役場へ申請することによって「個人番号カード」を受け取ることができます。 (個人番号カード交付申請の手数料は当面無料です。) ・この個人番号カードが本人確認を行う身分証明書の役割を持ちます。 ・番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。また、個人番号カードを紛失した際の再発行の際は原則手数料が必要となりますので、管理に気をつけ大切にして下さい! |
| 国民の一人ひとりにマイナンバー(12ケタの個人番号)が割り当てられ、 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用がはじまります。 それに伴い、民間事業者も、税や社会保険の手続のため、従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります! ☆ マイナンバーを取得する従業員とは「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト」です ☆「海外社員」「出向社員」「派遣社員」は対象外です。
従業員等からの個人番号取得について。
※従業員が事業者に対してマイナンバー提示することは法令上の義務です。 拒否することはできません。 |
| 主な提出書類の例 | 施行日 | |
| 【社会保障分野】
| ・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者資格喪失届 | 平成28年 1月1日提出分~ |
| ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 平成29年 1月1日提出分~ | |
| 【税分野】 | ・給与所得ならびに退職所得の源泉徴収票 ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 ・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 ・不動産の使用料等の支払調書
平成28年中に「退職者がいた」「税理士等への報酬を支払った」 このような場合に番号を確認し保管しておく必要があります。 | 平成28年の1月1日の 属する年分の申告から
|
| 従業員から集めたマイナンバー(個人番号)は、事務に必要な限りは保管します。
☆パソコンで保管する場合はセキュリティ対策をしっかり行います。 インターネットに接続されている場合はウィルス対策ソフトを最新版に更新し、担当者だけが扱えるようパスワードによる保護をするなどして対応しましょう。
☆上記のような対応ができなければ、書類にて管理しましょう。 その際にも担当者だけが扱えるような対応を行って下さい。(カギの付いた棚や引き出しで管理するなど) 無理にパソコンを購入することもありません。
【保管の期限】 書類によって法令で定められていますので下記の表を参考にして下さい。
たとえば、源泉徴収簿や扶養控除等申告書は在籍していた年の翌年の1月10日から7年を経過する日まで保存期間とされています。
保管の期間が過ぎた場合にはマイナンバーを出来るだけ速やかに廃棄または削除することになるとされています。 その際はシュレッダーでの廃棄や溶解処分を行い、そのことを記録しておく。
|
| 特定個人情報が漏えいすると、その情報を使って個人になりすまし、重大な犯罪に悪用される危険性があります。 そのようなことが起きないように事業者は厳重な管理体制を整えることが求められています。 ずさんな管理を行ったり、不正利用を行った場合には事業者に大きなリスクが及ぶことになります。
【予測されるリスク】 ①法律上のリスク 個人番号を不正に利用したり、正当な理由がなく提供する。また、不正により他人の個人番号カードを取得した場合などには懲役もしくは罰金、またはその併科とされています。
②信用上のリスク 個人情報の取り扱いがルーズだという事になってしまうと、重要な取引を失ったり、入札に参加できないといったケースなどが予想されます。また、従業員からの信頼を失い離職に繋がることも考えられます。
③民事上のリスク 特定個人情報を漏えいされた従業員が事業者を損害賠償で訴えることも考えられます。 マイナンバーを含む特定個人情報は、その重要性の高さから今までよりも高い水準の損害賠償金額となる可能性があります。
上記のようなリスクがあることを認識し、安全管理体制をしっかりと整えましょう。 |
従業員数の少ない事業所では、以下を参考にして下さい!!
| 〈担当者の明確化と番号の取得〉 ◇マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう。(給料や社会保険を扱っている人など)
◇マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を本人に通知するか公表しましょう。 ※個人情報保護法第18条により定められています。 また、明示した利用目的以外でのマイナンバー利用は出来ませんのでご注意ください。
◇マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。 ①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。 ※従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認して下さい。 ※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。
〈マイナンバーの管理・保管〉 あらかじめ決めておいた担当者以外のものに勝手に見られないように、下記の対応を行いましょう。 ◇マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管する。 無理にパソコンを購入する必要はありません。
◇パソコンでマイナンバーを扱う際の注意。インターネットに接続されている場合はウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行う。その他に、パスワードによる保護などが考えられます。 このような対応ができない場合は、前項の対応を行って下さい。
◇従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
☚チェックリストの確認はこちらをクリック! マイナンバー社会保障・税番号制度ページより(内閣官房) |